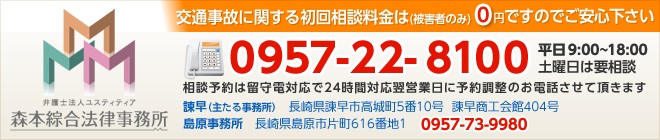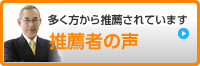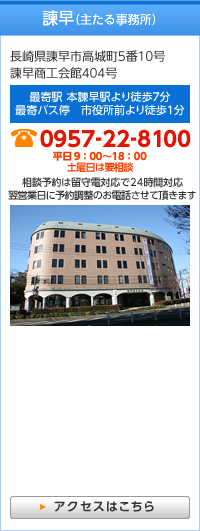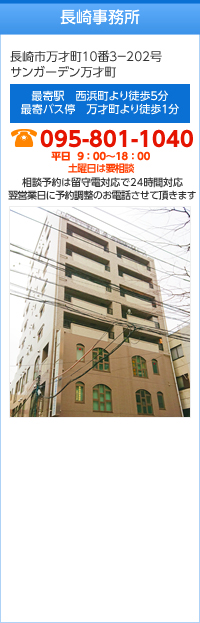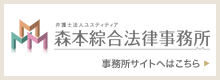RSD(Reflex Sympathetic Dystrophy 反射性交感神経性ジストロフィー)とは?
交通事故に遭い怪我をしたとき、人間の体は怪我を少しでも早く治そうと出血を止めるために血管を収縮させます。
この血管は怪我が治れば通常、日常的な状態に戻るようになっていますが、この血管が元に戻らない状態になる方もいらっしゃいます。
そうなると、血管が戻らないことによって血流不足が発生し、怪我をした箇所がズキズキと痛んだり、灼熱痛が起こります。
この状態をRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)やCRPS TypeⅠ(複合性局所疼痛症候群)と呼びます。
交通事故に遭った後に、このような症状が発症するようであれば、RSDである可能性が考えられます。
RSDとは、交感神経の異常な反射亢進を基盤とする疼痛、腫脹、関節拘縮等を特徴とする病態です。
その発生機序について、一般的には次のように説明されています。
外傷を受けると、正常な交感神経反射が起こり、出血を止めたり、余分な腫脹を防ぐために四肢の血管は収縮します。
そして外傷が治癒すると反射は消失します。
しかし、RSDの患者はこの反射が消失せずに働き続け,末梢の組織に強い交感神経亢進状態が続くことになります。
これが,局所を虚血状態にし、より強い持続的な痛みとなって悪循環を形成し,RSDを発症することになると言われています。
RSDの主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化(栄養障害)とされています(RSDの4主徴)。
ほかに、抹消循環不全、発汗異常、骨萎縮、筋萎縮、手掌腱膜炎などの症状が現れることもあります。
疼痛は、原因となる外傷に不つり合いに強烈なことが特徴的で、typeⅠでは、うずくような疼痛が、typeⅡでは、加えて灼熱痛(burning pain)が見られます。
また,異痛症(allodynia)や痛覚過敏(hyperalgesia)が起こります。
自賠責におけるRSDの等級認定の際、ポイントとなるのは以下の3点です。
① 関節拘縮
② 骨の萎縮
③ 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)
これらの3点が健側と比較して明らかに認められる場合に限り,これら3点にかかる所見の程度及び関節拘縮の程度を参考にして、7級、9級、12級を認定することになっています。
これら3点
の要件を立証しなければRSDの等級認定は難しいことになります。
の要件を立証しなければRSDの等級認定は難しいことになります。
この3点について客観的な診断をしていただくためにも、まずはRSDに詳しい医師からに診断をしていただき、後遺障害診断書や後遺障害等級認定を得るために必要となる資料を揃える必要があります。
等級認定基準
| 等級 | 認定基準 |
| 第7級 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
|
| 第9級 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 通常の労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
| 第12級 |
局部に頑固な神経症状を残すもの
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの
|
当事務所では、適正な後遺障害等級認定の獲得のサポートから、適正な賠償金の獲得までトータルで被害者の方に寄り添う形でサポートさせていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。